2017年1月24日作成開始 2020年8月24日更新

1977年に発売されたカセットデッキです。
カセットメカのグリス固着除去とベルト交換、電解コンデンサーと半固定抵抗の交換。
スイッチとボリュームの分解清掃、各種調整。
★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★
SONY TC-K5の修理
2017年1月24日作成開始 2020年8月24日更新

1977年に発売されたカセットデッキです。
カセットメカのグリス固着除去とベルト交換、電解コンデンサーと半固定抵抗の交換。
スイッチとボリュームの分解清掃、各種調整。
★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★
| TC-K5の特徴と主な規格 | |
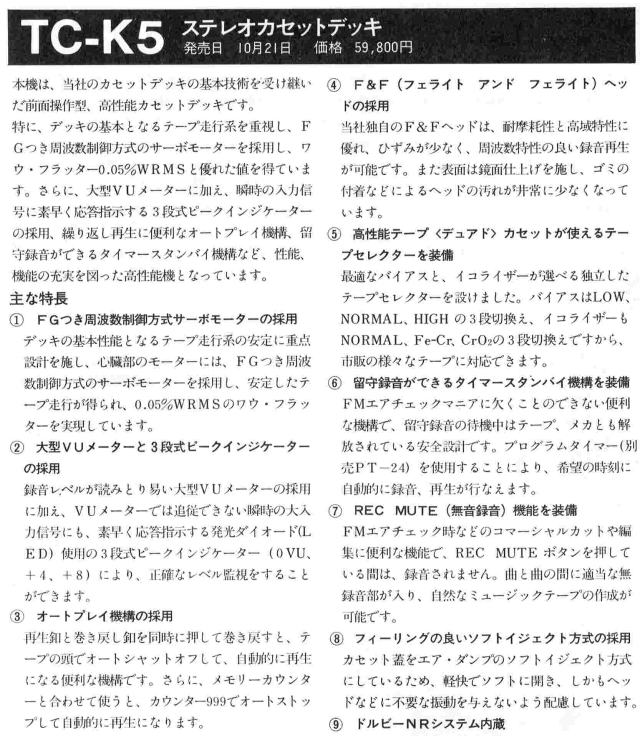 ソニーの新製品資料 |
|
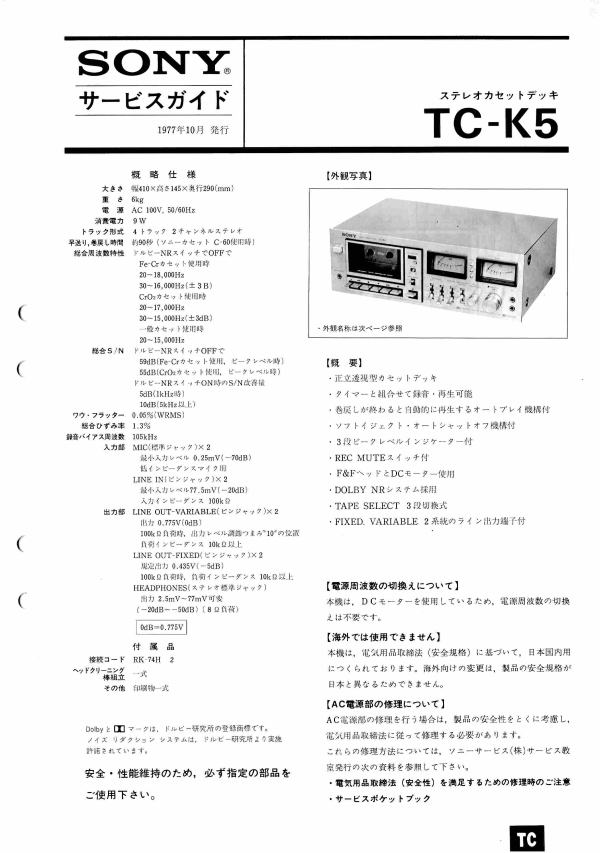 TC-K5のサービスガイド |
|
| 1台目の分解作業 | |
 正面パネルと操作キーとつまみは、 きれいではありません。 |
 中のカセットメカや部品はきれいです。 グリーンモーターが目立ちます。 |
 |
 |
 |
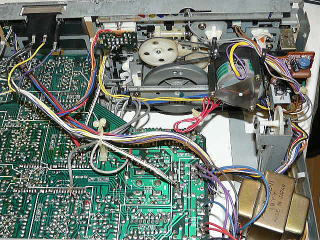 |
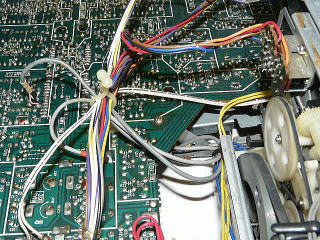 |
 |
 |
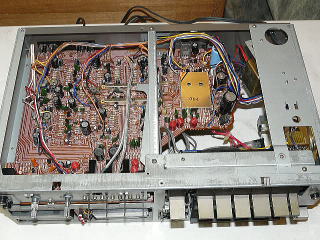 |
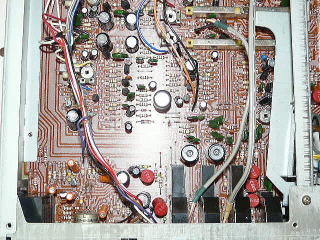 |
 |
 |
 |
 |
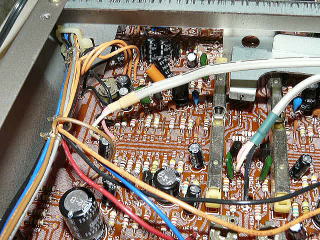 |
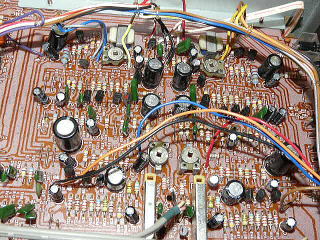 |
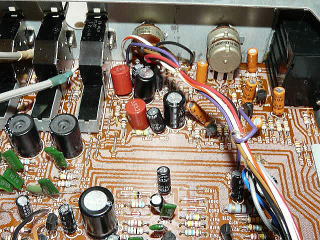 |
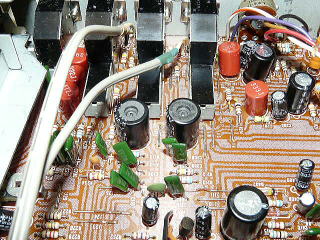 |
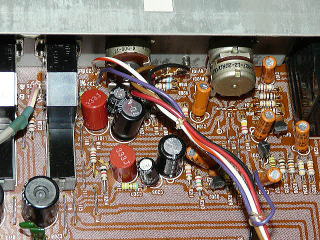 |
 |
 |
 |
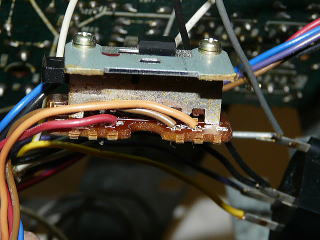 |
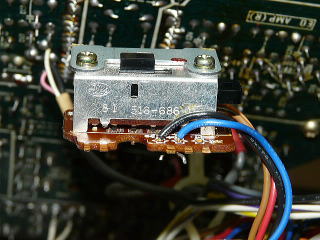 |
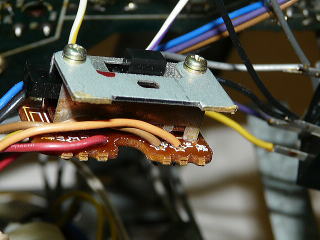 |
 |
ベルトを取り出して寸法を調べました。 交換する電解コンデンサーと半固定抵抗の 値を調べます。 しばらく作業時間がないので、 一旦元通りに組み立てます。 |
| 2台目の分解作業 | |
 正面パネルはきれいです。 |
 カセットメカの樹脂は少し黄ばんでいます。 |
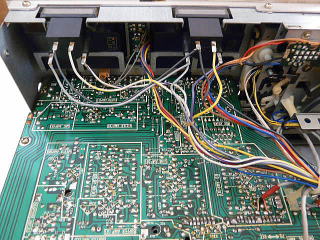 |
 |
 作業手順は手探りで分解なので、 効率の良い分解手順ではありません。 |
 後で分かりましたが、メカ内の化粧板を 先に外すとメカは取り出しやすくなります。 |
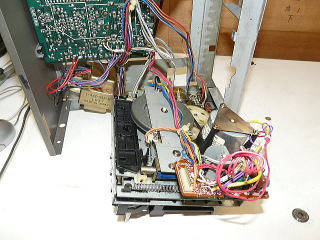 |
 |
 グリーンモーターのシールがありません。 |
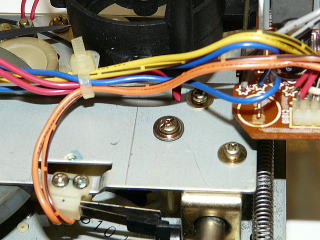 |
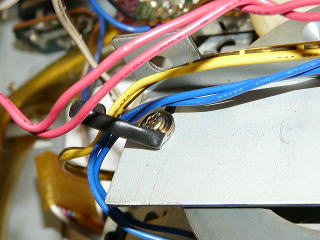 |
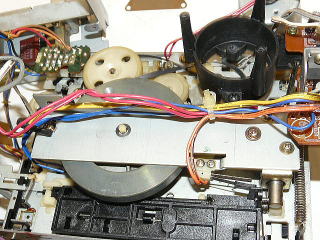 |
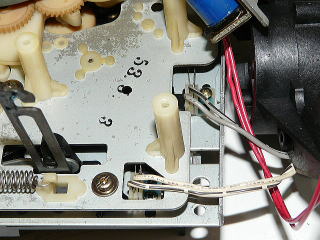 |
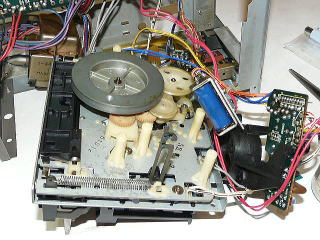 |
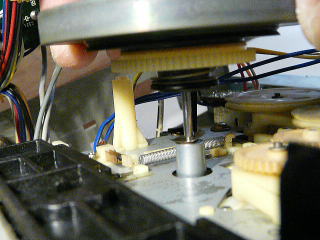 |
 |
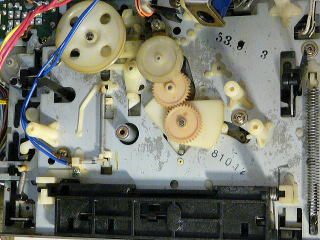 |
 |
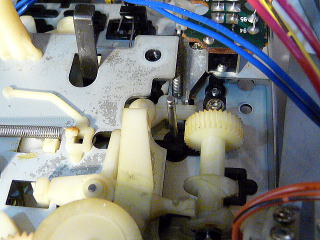 |
 |
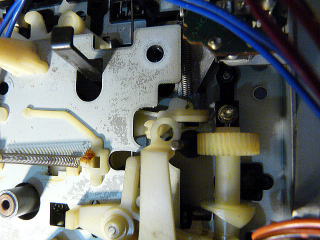 |
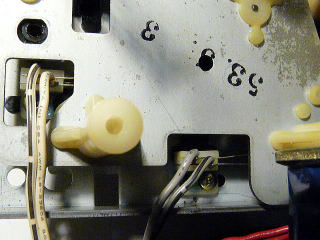 |
 |
 |
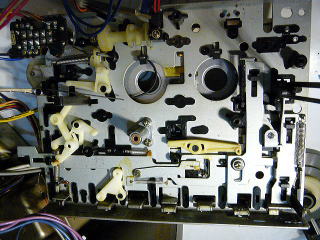 できれば、先にカウンターのベルトを 外します。 |
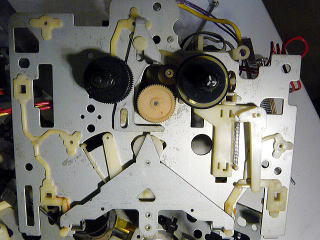 |
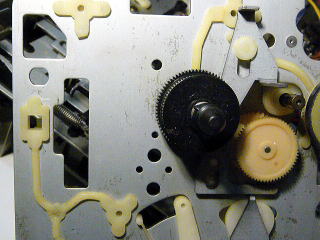 |
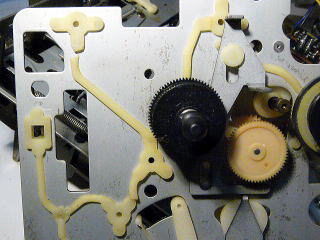 |
 |
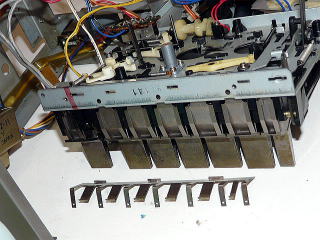 |
| 1台目の分解作業を再開して比較 | |
 1台目のモーターの型番 2台目と同じ型番です。 |
 1台目はグリーンモーターの シールが貼ってあります。 |
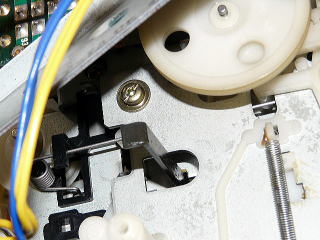 バネの位置を確認 |
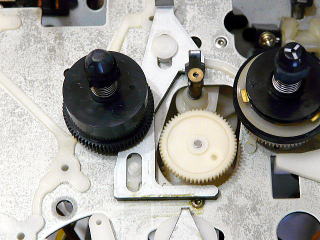 部品がなくなっています。 |
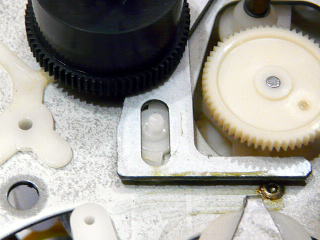 部品はあるので、後で取り付けます。 |
 シャットオフレバーの部品に クラックがあります。 |
 1台目のシャットオフレバーを取り外す。 |
 1台目のシャットオフレバーの修理。 |
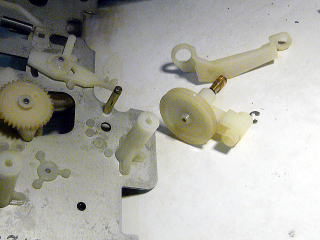 プーリを外すと作業しやすいです。 |
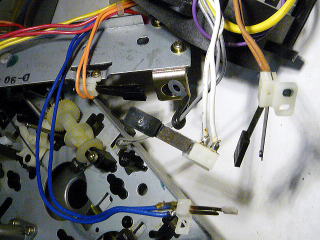 リーフスイッチを磨きます。 |
 メカの製造日が印刷されています。 |
1台目は昭和53年5月3日。 2台目は昭和53年1月23日。 同じ年でもモーターには、 グリーンモーターのシールが 無いものもあるようです。 |
 一台目、外れていた樹脂部品を接着 |
 モーター取り付けの樹脂製の柱も接着 |
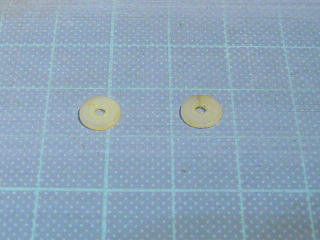 1台目に、2つ外れて落ちていました。 |
 このスライダをおさえる部品のようです。 |
 2台ともここの固定用部品が 外れていました。 |
 取り付けるとクラックが広がります。 |
 2ミリねじなどに使用する丸座金を 用意します。 |
 補強に瞬間接着剤で固定して おきます。 |
 1台目も外れています。 |
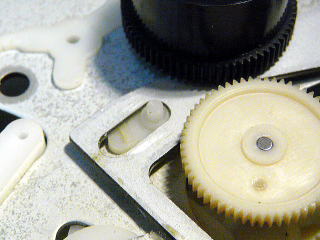 1台目も同じ修理をします。 |
 瞬間接着剤が垂れないように 気をつけます。 |
 補強しておきます。 |
 2台目のモーターのプーリーを磨きます。 |
 磨きました。 |
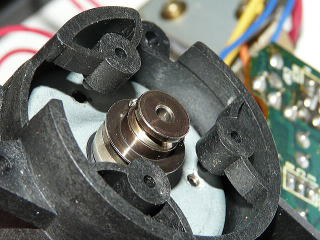 モーターのねじ穴とゴムの突起を 合わせます。 |
 モーターを押さえ板で固定します。 |
 1台目のモーターも取り外します。 |
 プーリーを磨きます。 |
 磨きました。 |
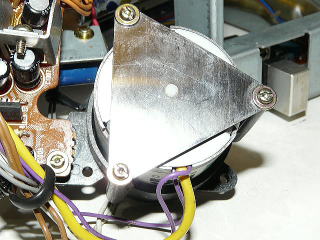 取り付けます。 |
 1台目。 ゴムとベルトをかける溝を クリーニングします。 |
 2台目。 ゴムとベルトをかける溝を クリーニングします。 |
 2台目。プーリの溝を磨きます。 |
 1台目。プーリの溝を磨きます。 |
 2台目のスライダを取り付けます。 |
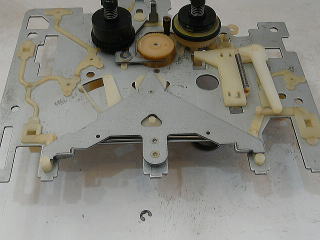 2台目のスライダを取り付けました。 |
 2台目のスライダをEリングで固定。 |
 1台目のスライダをEリングで固定。 |
 リーフスイッチに接点改質剤を塗布。 |
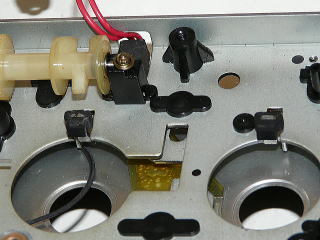 ブレーキのゴムを拭きます。 |
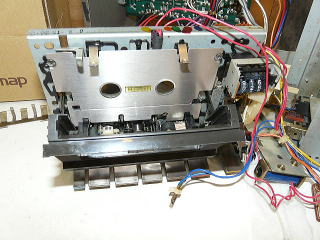 1台目の化粧板を取り外します。 |
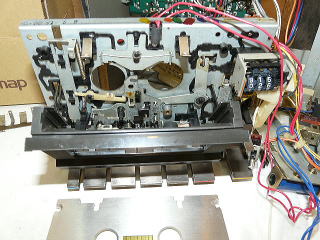 化粧板を取り外しました。 |
 カウンターのゴムベルトを外します。 |
 カセットホルダー右側のEリングを 外します。 |
 カセットホルダー左側のEリングを 外します。 |
 カセットホルダ左側。 |
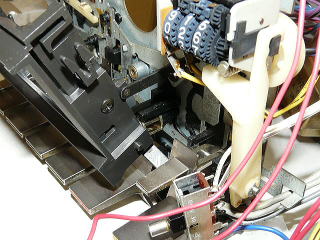 カセットホルダー右側。 |
 カセットホルダー右側のEリングを 外しました。 |
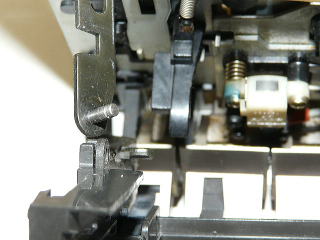 カセットホルダー左側のEリングを 外しました。 |
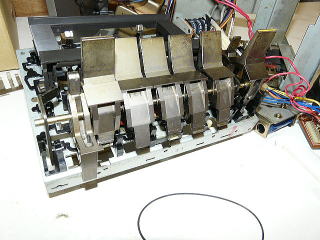 操作レバーの取り外し。 |
 ポーズレバーはスプリングがついています。 |
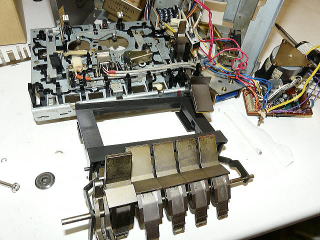 ポーズレバーを残して取り外しました。 |
 ポーズレバーのバネを外します。 |
 カセットホルダーと操作レバーが分離。 |
 カセットホルダーの樹脂部分は、 両サイドと正面のねじで固定されています。 |
 操作レバーの裏側には番号があります。 ばらす前に、順番を記録しておきます。 |
 番号と形を確認 |
 番号と形を確認 |
 古いグリスをふき取るため、 更に分解します。 |
 ピンチローラーを外します。 |
 Eリングとバネを外します。 |
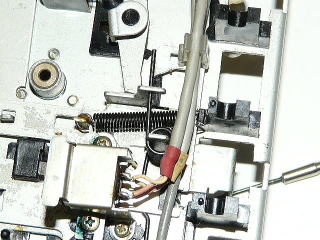 ヘッドブロックを外すため、バネを外します。 |
 バネを外しました。 |
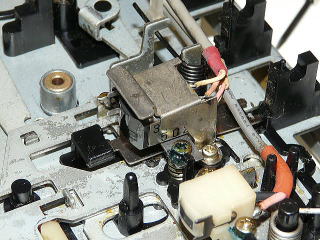 ヘッドの下の板バネを、 上へスライドさせます。 |
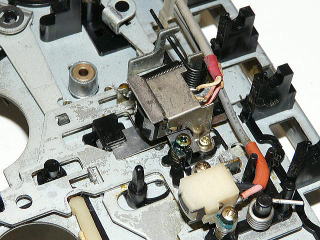 写真で見ると左側にスライドさせて 外します。 |
 板ばねの下には、スチールボールが あります。 |
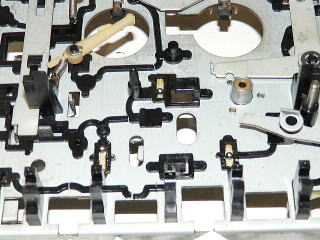 スチールボールが3か所にあります。 |
 板ばねの下は小さいです。 大きさが違います。 |
 ヘッド基板です。 |
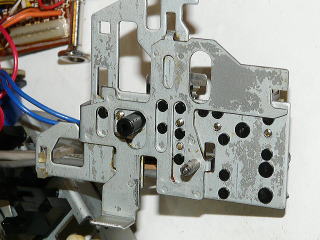 リミッター板と2枚重ねになっています。 |
 グリスと汚れをふき取ります。 |
 まだ部品を外します。 |
 タイマースタンバイのレバーを外します。 |
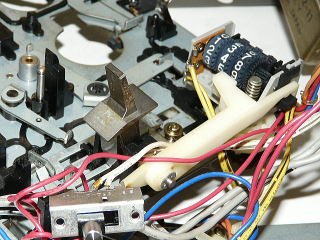 カウンターリセットレバーと繋がって います。 |
 Eリングを外すと分離できます。 |
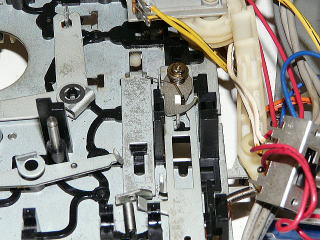 ポーズレバー固定バネの右側が 外れています。 |
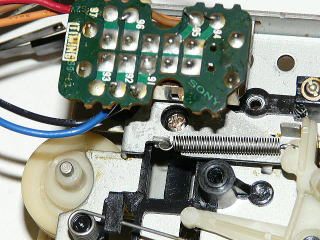 裏側のテープカウンターの固定ねじを 外します。 |
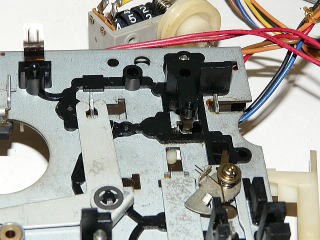 テープカウンターが外れます。 |
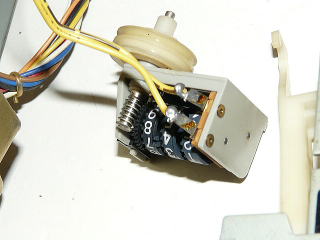 テープカウンターも磨いておきます。 |
 裏側のここも分解。 |
 古いグリスをふき取ります。 |
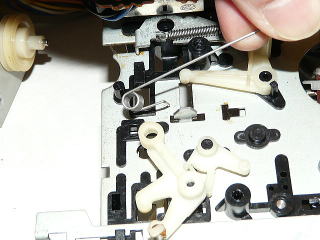 裏側のバネを外します。 |
 次にポーズロック部のネジを外します。 |
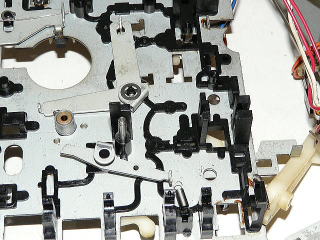 ポーズと隣のレバーを外します。 |
 取り外したレバー。 |
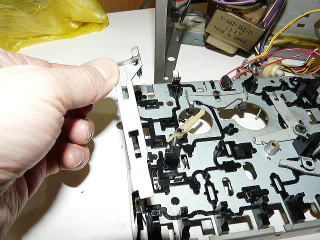 誤消去防止レバーを外します。 |
 ピンチローラー側の部品を外します。 |
 軸を固定している樹脂にクラックがあります。 |
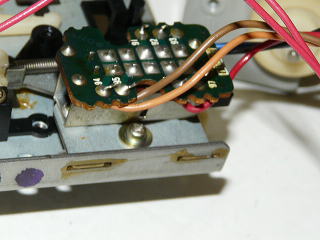 裏のタイミングスイッチの接着剤の ついている 取り付け位置に印をつけておきます。 |
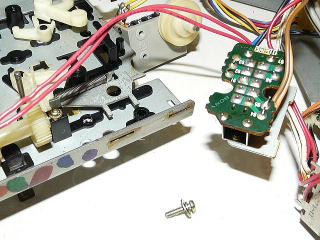 タイミングスイッチを外しました。 |
 レバーを外します。 |
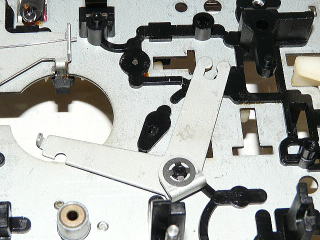 くの字のレバーが動きやすなります。 |
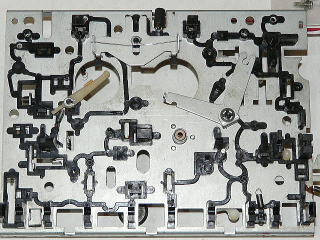 表側の外せる部品を外しました。 |
 電球も外します。 |
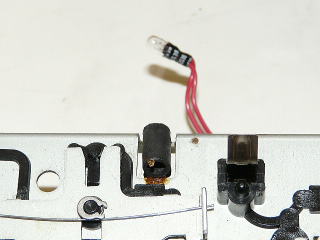 電球を外しました。 |
 分離できて作業がしやすくなります。 |
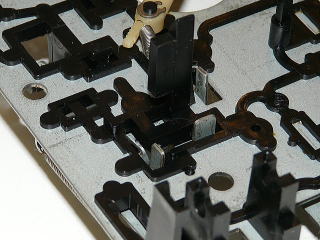 樹脂のクラックが大変多いです。 |
 かなり隙間があります。 |
 裏側も部品を外します。 |
 レバーを固定してるネジを外します。 |
 取り外しできました。 |
 横に長いレバーも外します。 |
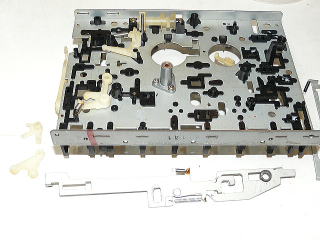 取り外しました。 |
 ピンチローラーの軸の裏側も クラックあり。 |
 クラックを瞬間接着剤で補修します。 |
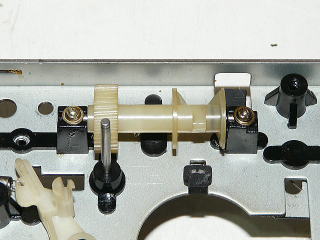 シャットオフのウォームホイールの 回転が少し重たいようです。 |
 取り外して、古いグリスをふき取ります。 |
 写真上、クランプ側にテフロンワッシャー と、間にスプリングが入ります。  |
 裏面、取り外した部品を取り付けます。 |
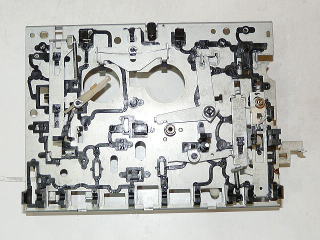 表面、取り外した部品を取り付けます。 |
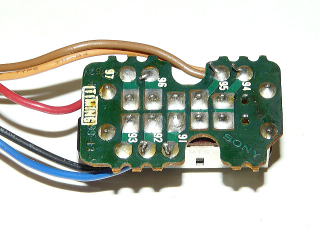 タイミングスイッチを分解清掃します。 |
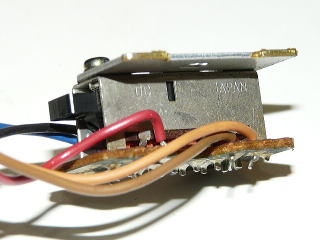 スイッチの向きを確認。 |
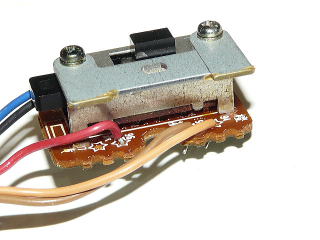 配線を確認。 |
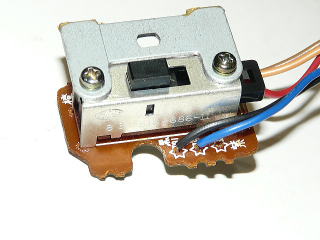 配線を確認。 |
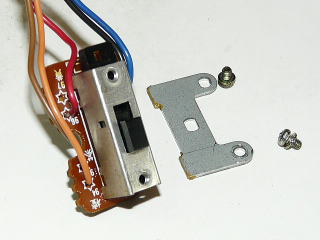 取り外します。 |
 スイッチを分離しました。 |
 分解します。 |
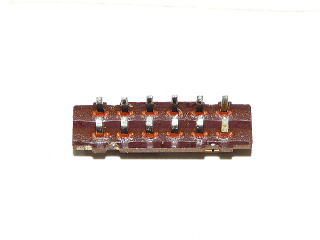 裏側を確認。 |
 かなり黒く汚れています。 |
 きれいに磨きます。 |
 接点改質剤を塗布します。 |
 樹脂部品をかぶせます。 |
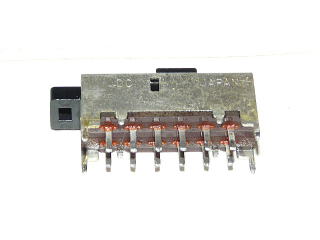 カバーを取り付けますが、 爪は曲げません。 テスターで導通テストをします。 |
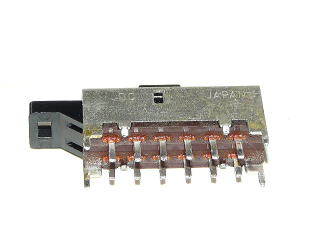 導通テストで問題がなかったのを 確認した後、変形しないようにツメを 曲げます。 |
 基板に取り付けます。 |
 メモリースイッチです。 |
 配線を確認。 |
 配線のついたまま分解します。 |
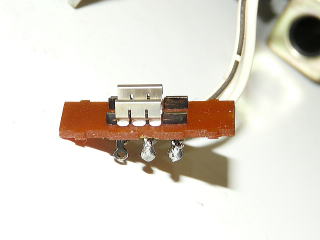 かなり黒くなっています。 |
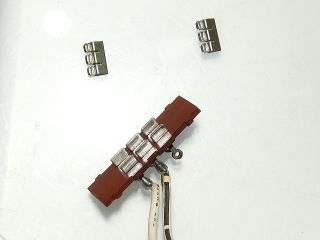 磨きました。 |
 接点改質剤を塗って組み立てます。 |
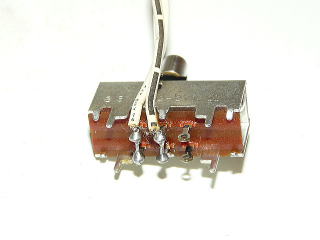 導通テストをしてから、 カバーの爪を曲げます。 |
| カセットメカの組み立て | |
 ヘッド基板とピンチローラーを取り付け。 |
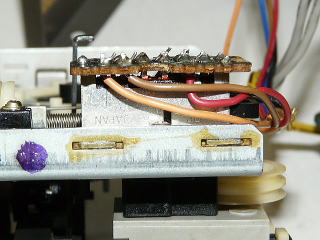 タイミングスイッチを元に取り付けて あった位置に追わせて取り付けます。 |
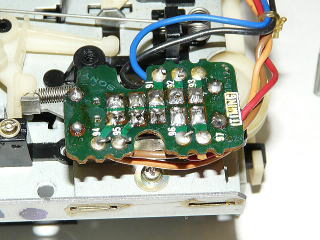 ネジで固定します。 |
 イジェクトレバーのバネを一旦外します。 |
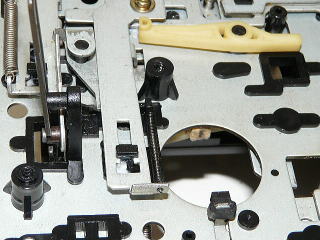 巻き戻しのレバーのバネも一旦外します。 |
 操作ボタンを取り付けます。 |
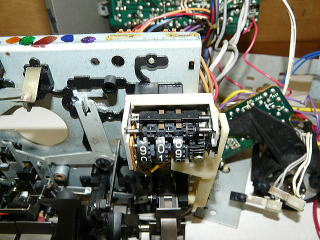 カウンターを取り付けます。 |
 カセットホルダーを閉じた状態。 |
 操作ボタンの固定用バネにグリスを 塗ります。 |
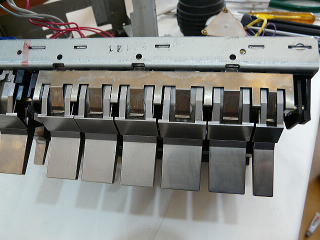 3つのツメを先にはめてから取り 付けます。 |
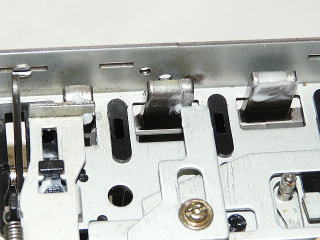 操作ボタンとレバーの間にグリスを 塗ります。 |
 操作ボタンとレバーの間にグリスを 塗ります。 |
 ロック板とバネを一緒に取り付けます。 |
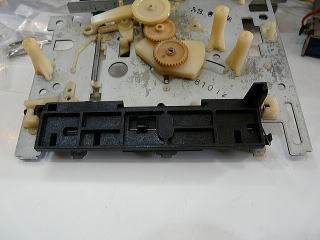 バネを掛けます。 |
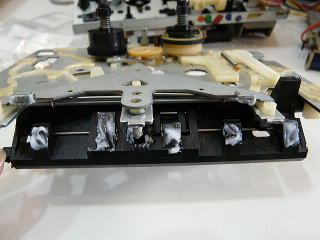 ロック板にグリスを塗ります。 |
 ブレーキスライドを持ち上げてから 取り付けます。 |
 バネの位置を確認。 |
 部品を連結。 |
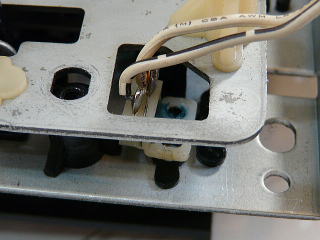 リーフスイッチの取り付け。 |
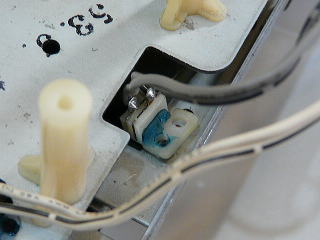 リーフスイッチの取り付け。 |
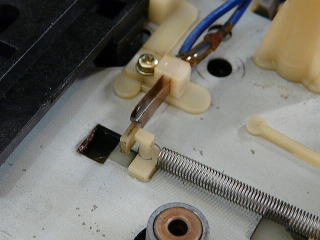 リーフスイッチの取り付け。 |
 ネジで固定。 |
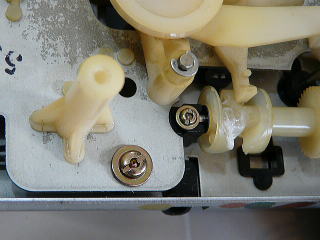 ネジで固定。 |
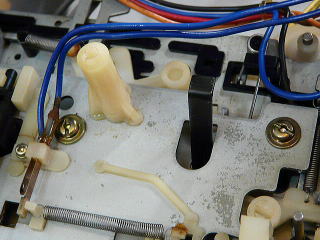 ネジで固定。 |
 ネジで固定。 |
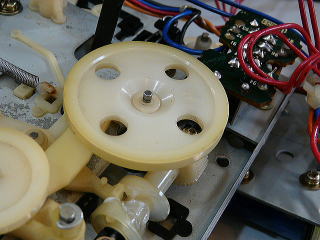 プーリの取り付け。 |
 ワッシャを先に取り付け。 |
 Eリングで固定。 |
 フライホイール。 |
 バネとワッシャの取り付け。 |
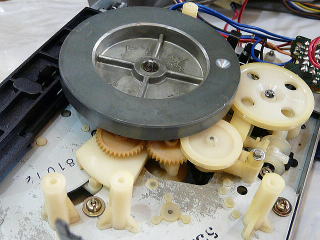 軸に通します。 |
 ベルトを掛けます。 |
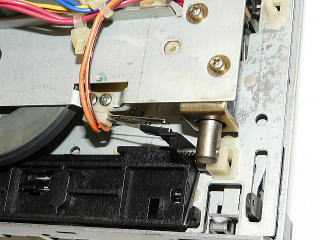 フライホイール押さえ板とソレノイドの 取り付け。 |
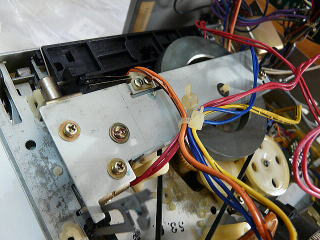 ネジで固定。 |
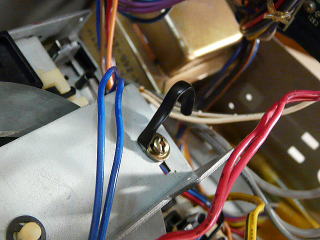 ネジで固定。 |
 イジェクト用のバネを取り付け。 |
 バネを掛けます。 |
 モーターとサーボ基板の取り付け。 |
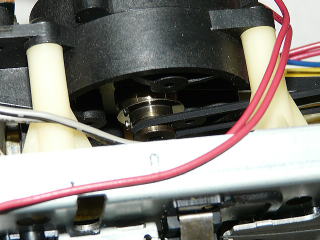 ベルトを掛けます。 |
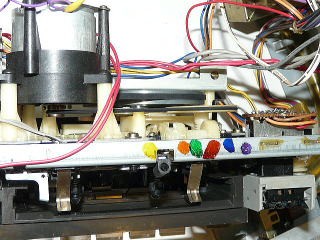 ベルトを掛けます。 |
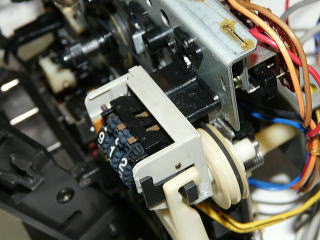 カウンターのベルトを掛けます。 |
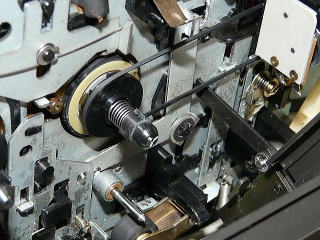 カウンタのベルトをリール台に掛けます。 |
 電球を取り付けます。 |
 化粧板を取り付けます。 |
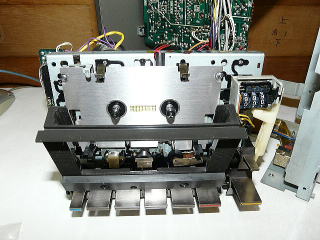 この時は化粧板を取り付けましたが、 メカをシャーシに取り付け後が良いです。 |
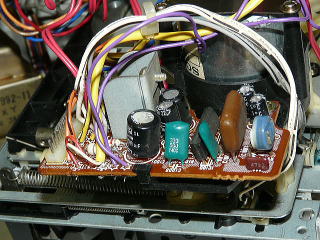 サーボ基板の部品は後で取り替えます。 |
 カウンターのリセットレバーを一旦 取り外します。 |
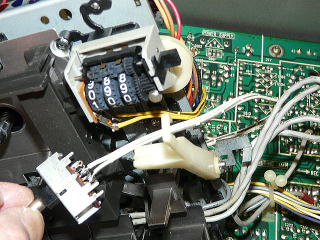 メモリーのスイッチを通します。 |
 リセットレバーを元通り取り付けます。 |
 カセットメカとシャーシの固定用ネジ穴は 化粧板とカセットメカの間に来ます。 |
 メモリーのスイッチを取り付けます。 |
 カセットメカを仮固定します。 |
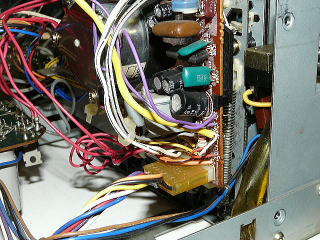 サーボ基板にコネクターを取り付けます。 |
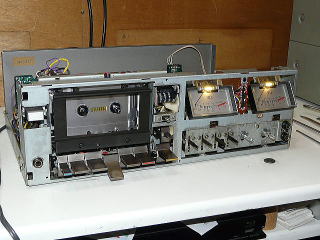 簡単なメカの動作テストをします。 |
 他のデッキで録音したテープ で 再生テスト。 |
 録音テストをします。 |
 自己録音再生はできました。 |
カセットメカの分解と組み立ては うまくいったようです。 次は、スイッチの接点洗浄や 電子部品の交換をします。 |
| 電解コンデンサと半固定抵抗の交換と録再切換スイッチの分解 | |
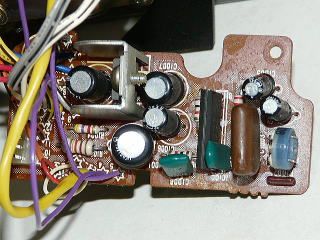 サーボ基板。 |
 電解コンデンサと半固定抵抗を交換。 |
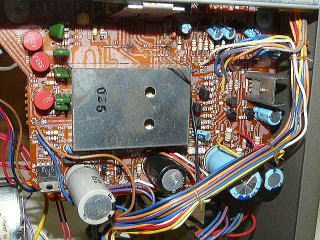 バイアス発振回路と電源回路。 |
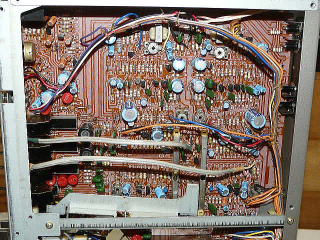 オーディオ回路。 |
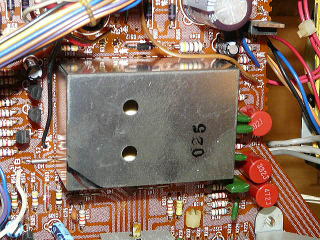 バイアス発信回路のシールドを外します。 |
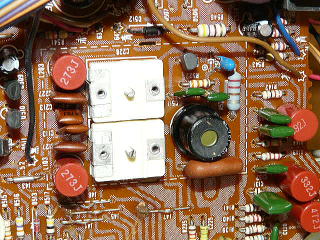 シールドを外した状態。 |
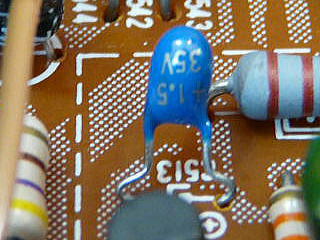 タンタルコンデンサがあります。 |
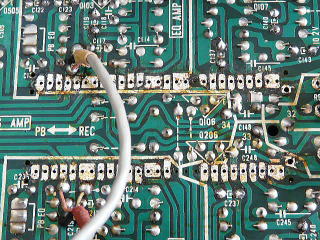 録再切換スイッチのハンダを吸い取ります。 |
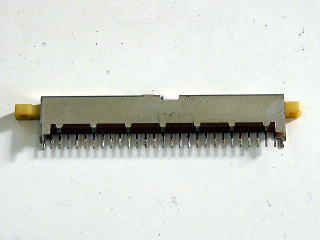 左チャンネルの録再切換スイッチ。 |
 バネを取り出します。 |
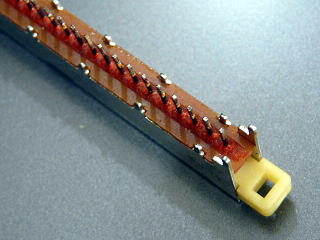 ツメを起こします。 |
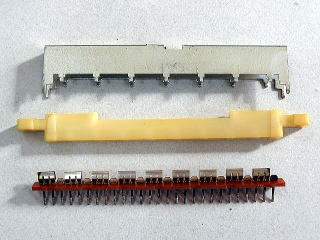 カバーを外します。 |
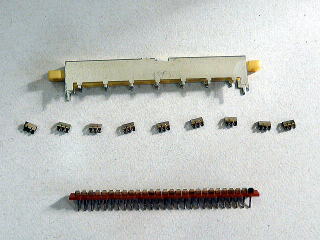 接点を磨きます。 |
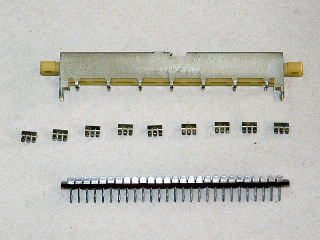 綺麗に磨きました。 |
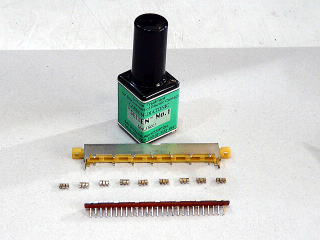 接点改質剤を塗ります。 |
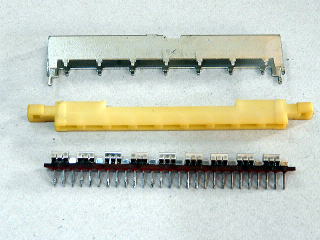 接点を組み立てます。 |
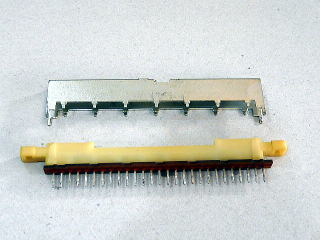 樹脂カバーを被せます。 |
 金属カバーを被せます。 |
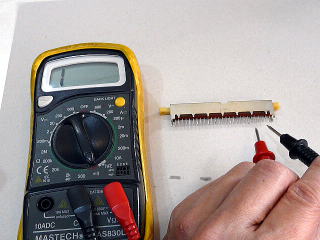 テスターで導通チェックをします。 |
 ツメを曲げます。 |
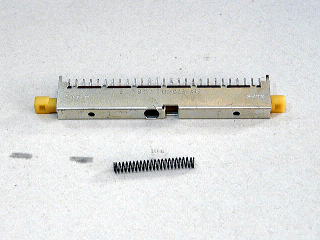 バネを入れます。 |
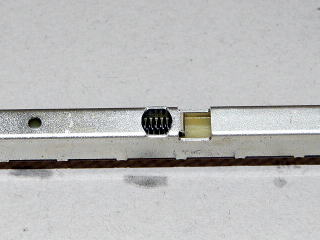 バネの入った状態。 |
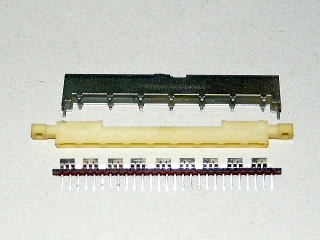 右チャンネルも同じ作業をします。 |
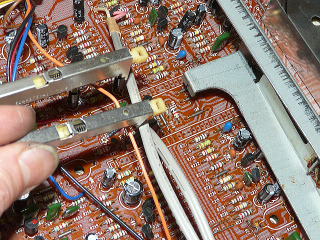 基板に取り付けます。 |
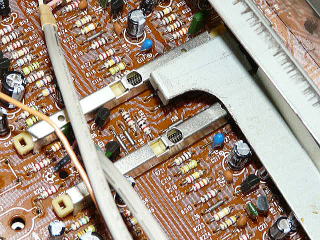 録音レバーを取り外します。 |
 レバーを取り外した状態でハンダ付け をします。 |
 古いグリスを拭き、新しいグリスを 塗ります。 |
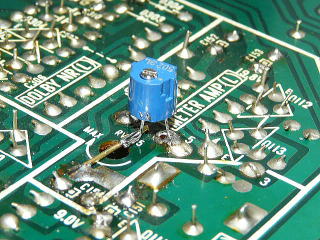 左METER AMPの半固定抵抗を交換。 |
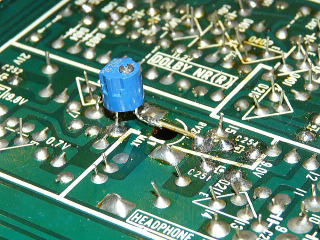 右メMETER AMPの半固定抵抗を交換。 |
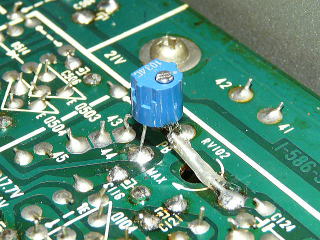 左EQ AMPの半固定抵抗を交換。 |
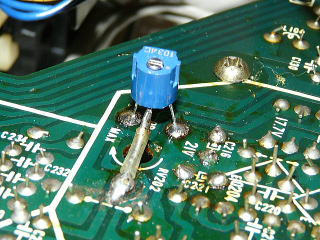 右EQ AMPの半固定抵抗を交換。 |
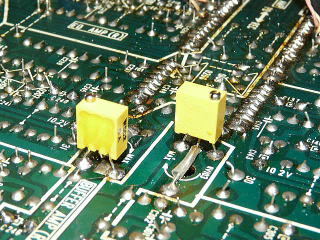 左右BUFFER AMPの半固定抵抗を交換。 |
 取り外した部品。 |
 半固定抵抗の足の延長に使えるもの。 |
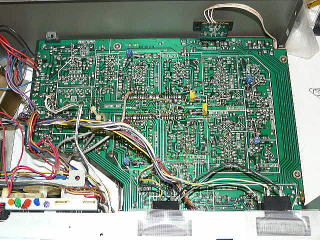 交換が終わったパターン面。 |
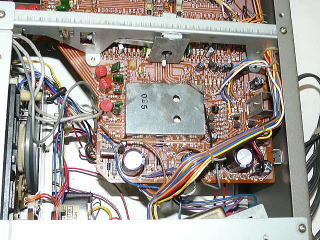 交換が終わった部品面。 |
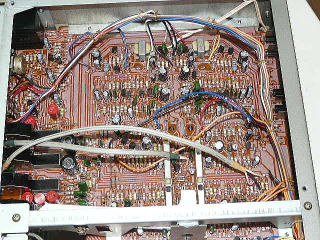 交換が終わった部品面。 |
次はスイッチなどに取り掛かります。 |
| テープ切換スイッチ(TAPE SELECT)、ドルビーNRスイッチ(DOLBY NR)、 入力切換/録音ミューティングスイッチ(INPUT SELECT/REC MUTE)の分解清掃 |
|
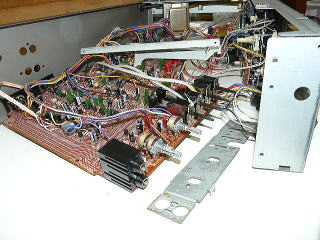 基板を取り外します。 |
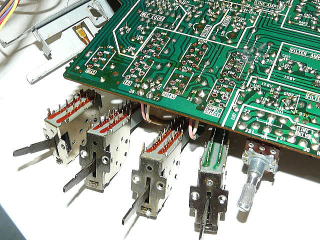 スイッチを取り外します。 |
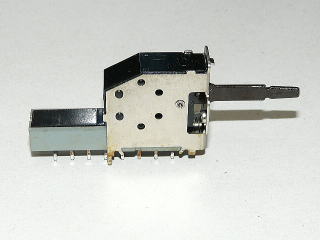 入力切換/録音ミューティングスイッチ |
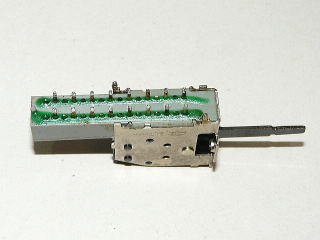 |
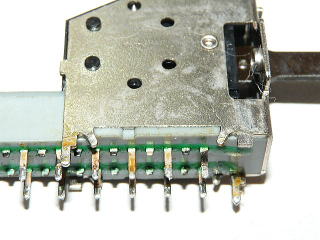 ツメを真っすぐにして分解します。 |
 接点を取り外します。 |
 接点を磨きます。 |
 |
 接点改質剤を塗ります。 |
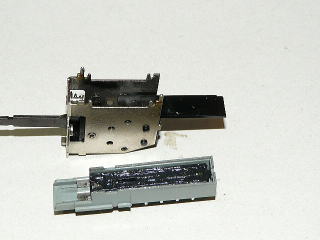 スライド面に接点グリスを塗っておきます。 |
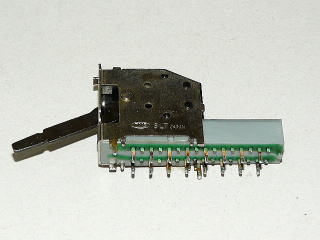 組み立てますが、まだツメは曲げません。 |
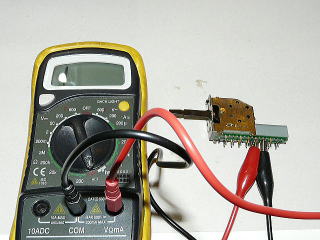 テスターで導通テストをします。 |
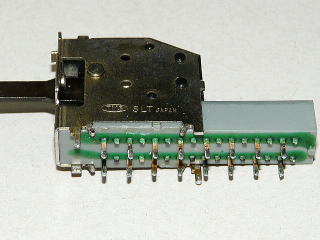 ツメを曲げます。 |
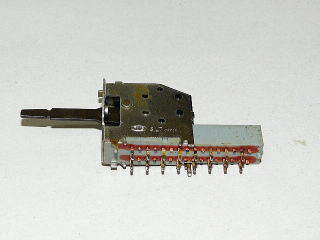 ドルビーNRスイッチ。 |
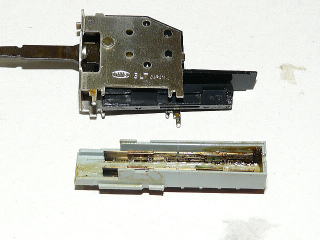 分解。 |
 磨きました。 |
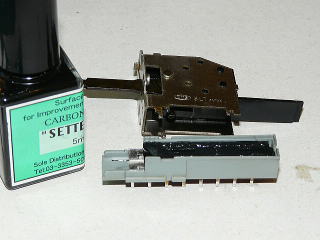 接点改質剤と接点グリスを塗布。 |
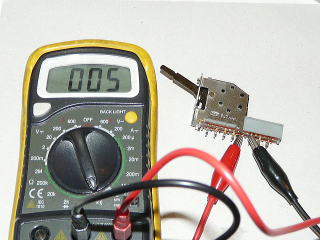 組み立てて導通テスト。 |
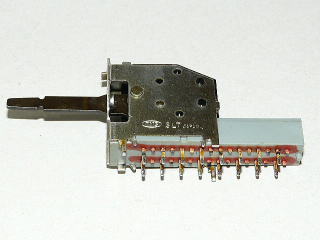 ツメを曲げます。 |
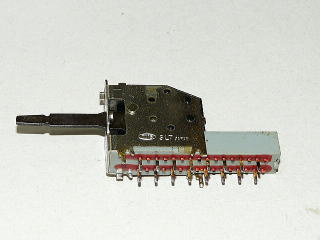 EQスイッチ。 |
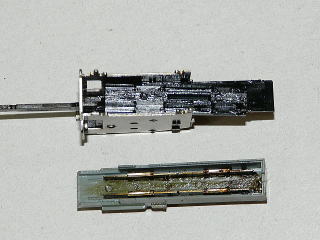 分解。 |
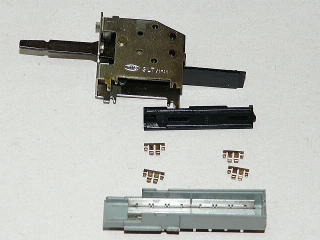 磨きました。 |
 接点改質剤と接点グリスを塗布。 |
 組み立てて導通テスト。 |
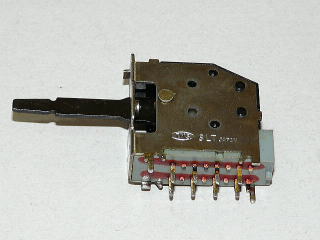 BIASスイッチ。 |
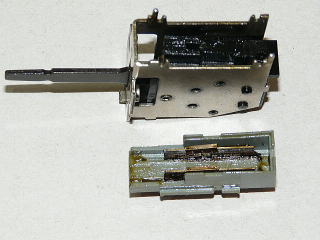 分解。 |
 磨いてから、接点改質剤と接点グリスを 塗布。 |
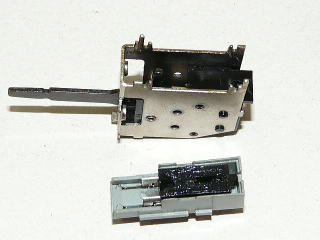 組み立て。 |
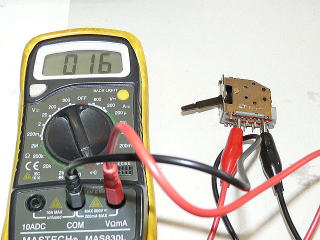 導通テスト。 |
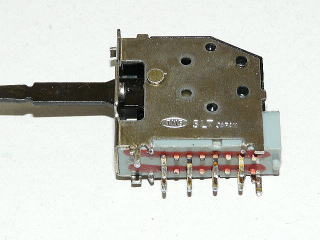 ツメを曲げます。 |
 位置決めに仮止めしています。 |
スイッチを先にハンダ付けしました。 |
| ヘッドホンボリューム/出力レベル調整(PHONES LEVEL/LINE OUT)、 録音レベル調整(REC LEVEL)の分解清掃。 |
|
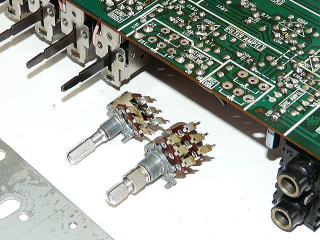 取り外します。 |
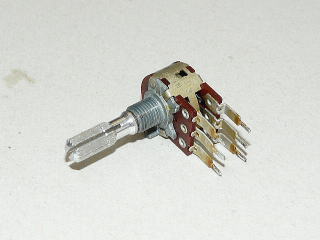 ヘッドホンボリューム/出力調整。 |
 ツメを起こして分解します。 |
 分解。 |
 接点を磨きます。 |
 接点改質剤を塗布。 |
 組み立て。 |
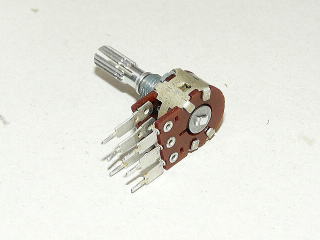 ツメを曲げます。 |
 導通テスト。 |
 録音レベル調整は分解しません。 接点洗浄剤と接点改質剤を塗布。 |
 導通テスト。 |
 パネルを取り付けてからハンダ付け。 |
| LINE INとLINE OUT端子を磨く | |
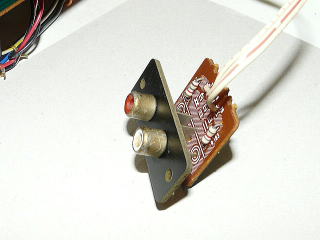 可変出力のLINE OUT端子。 |
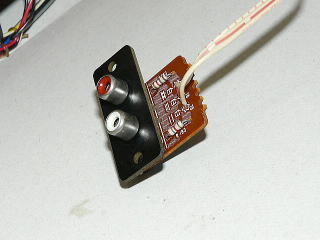 磨きました。 |
 LINE INとLINE OUT (固定出力)。 |
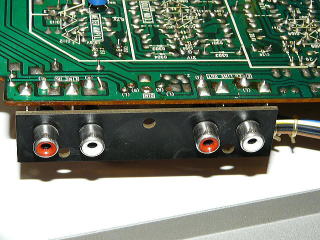 磨きました。 |
 シャーシへ組み込みます。 |
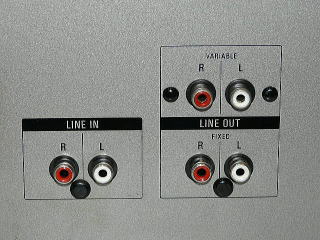 端子の固定。 |
 シャーシフレームの組み立て。 |
動作確認をします。 |
| 電球をLEDに交換 | |
 カセットホルダの電球。 |
 サーボ基板のコネクタ左上の赤い2本の配線。 |
 サーボ基板のパターン面。 |
 配線を外します。 |
 電球を定電流素子内蔵LEDの ホワイトに交換。 |
 定電流素子内蔵LEDに配線を 取り付けます。 |
 点灯テスト。 |
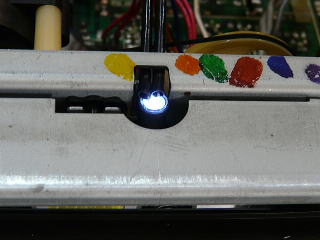 取付ます。 |
 消灯。 |
 点灯。 |
 録音表示ランプ。 |
 ピークレベルインジケーター基板の上の 2本の灰色の配線です。 |
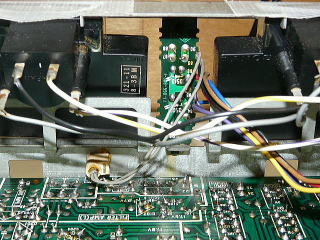 基板の裏。 |
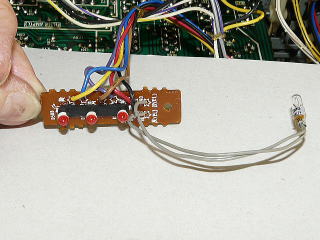 基板を取り出します。 |
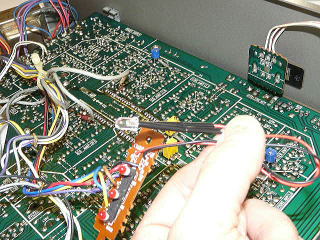 定電流素子内蔵LEDを取り付けてみます。 |
 点灯テストでは、まぶしすぎました。 |
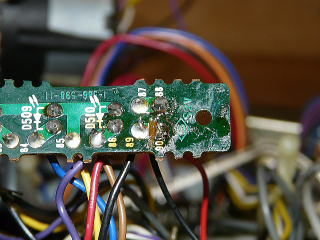 89と90のパターンの間をカットします。 |
 電流制限抵抗を付けます。 |
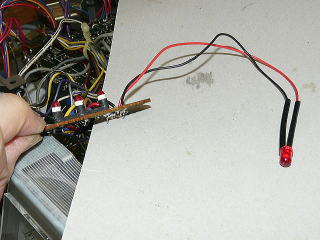 赤色LEDに交換。 |
 見やすい明るさになりました。 |
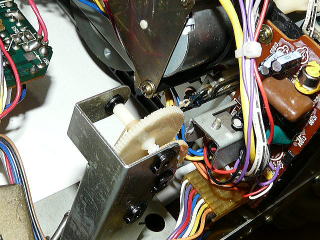 ソフトイジェクトのエアダンプを 取り付けます。 軸にオイルとギアにはグリスを 塗布すると動作音が静かになります。 |
 底板を取り付けます。 |
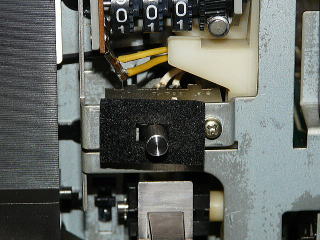 メモリースイッチにフエルトを取り 付けます。 |
 操作パネルを取り付けます。 |
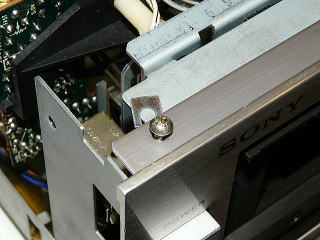 正面パネルを取りけます。 上のねじの間のコの字のスペーサーは、 右中左で厚みが違うものがありますので、 間違えないように取り付けます。 |
 ツマミを取り付けます。 |
| 各種調整 | |
 調整用にミリバルを接続します。 |
 固定出力を使用します。 |
 100kΩの負荷抵抗を間に入れます。 |
 クリーニングと消磁をしてから、 テープパスを見ます。 |
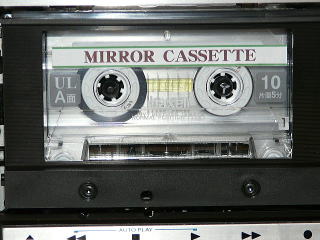 問題ありません。 |
 テープスピードの調整をします。 |
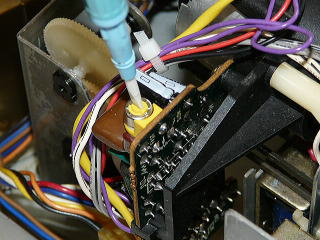 調整用の半固定抵抗を回します。 |
 3kHzに合わせます。 |
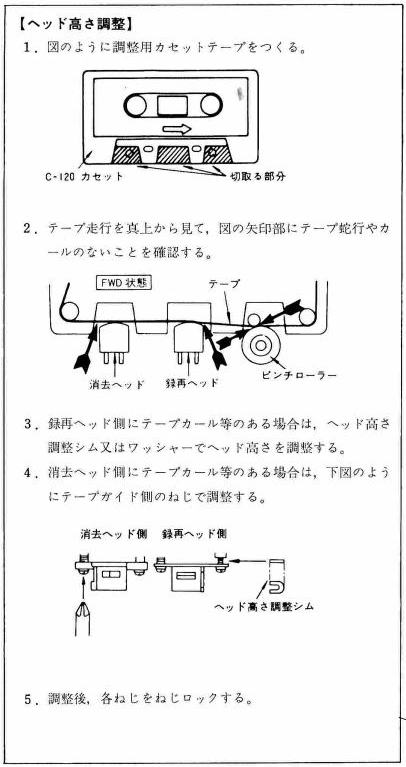 |
|
 録再ヘッドのペイントロックをはがします。 |
 6.3kHzで位相を見ながら合わせてみます。 |
 |
 |
 一応合わせました。 |
 一旦、0VUで左右再生レベルを 合わせ直します。 |
 10kHzで位相を合わせ直します。 |
 ペイントロックをします。 |
 もう一度、0VUの再生レベルを 合わせます。 |
 0VUは、435mVに合わせます。 |
 再生レベルの半固定抵抗を0VUに 合わせます。 |
 435mV。 |
 315Hz 0dBのテストテープを再生します。 |
 ミリバルのレンジを切換ています。 左右レベルを合わせます。 |
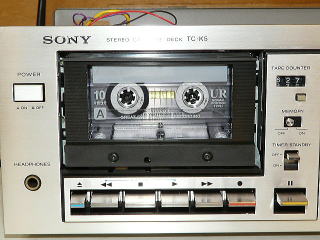 録音の調整は、インドネシア製に新しく なったマクセルURに合わせてみます。 |
 333Hzの信号。 |
 録音状態で、435mVに合わせます。 |
 メーターの半固定抵抗を、 0VUに合わせます。 |
 メーターを、0VUに合わせます。 |
 333Hzを0VU、バイアスを LOWにしてみます。 |
 -30dBにレベルを落として録音します。 |
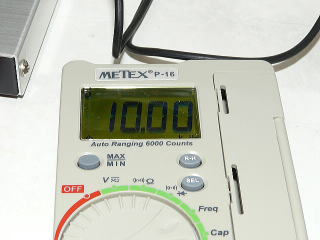 10kHzの信号を同じレベルで録音します。 |
 333Hzの再生レベル。 |
 10kHzの再生レベル。 |
 バイアスをNORMにして、 333Hzを-30dB録音。 |
 333Hzを再生。 |
 10kHzを再生。 バイアスはLOWではなく、 NORMのほうが良さそうです。 バイアスの調整をします。 |
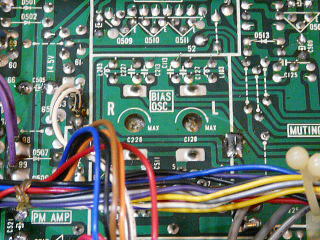 バイアスの調整箇所です。 マクセルURをNORMバイアスで、 333Hzと10kHzの-30dB信号が 録音と再生で同じになるように バイアスを調整します。 |
 333Hzの再生。 |
 10kHzの再生。 |
 次は、録音感度調整になります。 |
 333Hz 0VU 435mVに合わせます。 |
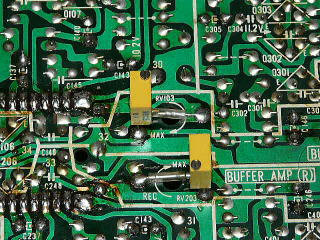 録音感度調整の半固定抵抗。 |
 0VUで録音。 |
 再生して左右のレベル差を確認。 |
 何度も繰り返して録音再生して レベル差をなくします。 |
 半固定抵抗は18回転のものなので、 微調整は大変楽になりました。 |
 左右同じレベルに追い込み出来ました。 録音と再生が0VUになるまで調整します。 |
 音楽を録音して音質チェックをします。 |
動作チェック中。 ほぼ終了に近づきました。 |
| カセットホルダー内の照明を調整 | |
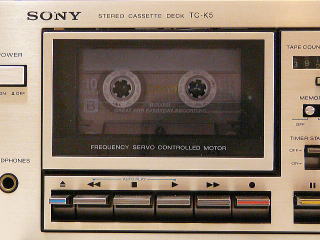 フタを取り付けると、照明が暗いです。 |
 取付ゴムの位置が良くありません。 |
 LEDの光は先端からしか出ていません。 |
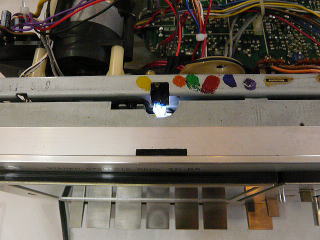 ゴムを外してみます。 |
 右半分が明るくなりました。 |
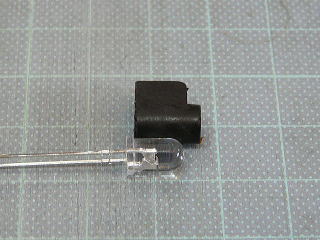 取付ゴムを加工してみます。 |
 2種類のサイズにカットしてみます。 |
 薄いサイズ。 |
 取り付けてみます。 |
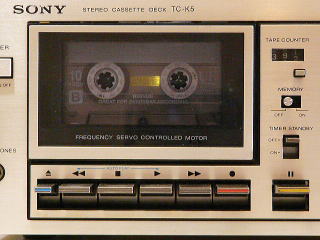 右側が明るくなりました。 |
 厚いサイズを取り付けます。 |
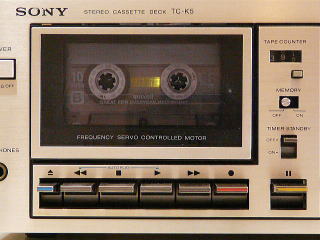 こちらも、右側だけ明るくなります。 |
 ゴムを外して結束バンドで固定します。 |
 ほぼ均一に明るくなりました。 |
 ネジ止め材で固定しておきます。 |
 一応、完成。 |
| 位相合わせ用アジマス調整テストテープの製作実験で再調整 | |
 「カセット用テストテープ路を作る Part5」で、位相合わせ用アジマス 調整用テストテープ製作に使用 するために整備しました。 |
 シングルキャプスタンのメカです。 バックテンショントルクが、 テープ走行にかなり作用します。 |
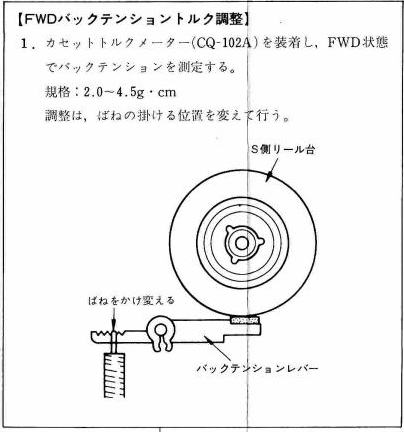 |
|
 サプライ側リール台の下の白いアームが、 バックテンションレバーです。 |
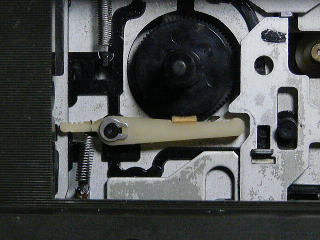 テープ再生時には バックテンションレバーが、 サプライ側のリール台に このように接触します。 |
 バックテンションレバーのスプリングの 位置を変えることで、 バックテンショントルクを変えられます。 どうやら、テープと周波数によって変更が 必要かもしれません。 |
バックテンショントルクを変えて 録音再生をし、 どう変化するか実験してみました。 |
 バックテンショントルクのスプリングの 位置を決めて、ミリバルと固定出力の間に 負荷抵抗100kΩを接続して回路の 再調整をします。 |
 化粧板を取り付けます。 バックテンショントルクを常時変える 場合は取り付けません。 |
 一応、化粧板を取り付けました。 |
 315Hz 0dBのテストテープを再生して 確認します。 |
 ミリバルのレンジを合わせます。 |
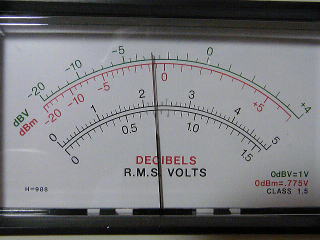 左右同じ値を示しています。 |
 VUメーターも左右合っています。 |
 315Hz 0VU(-4dB)のテストテープを再生。 |
 ミリバルのレンジを切換ます。 |
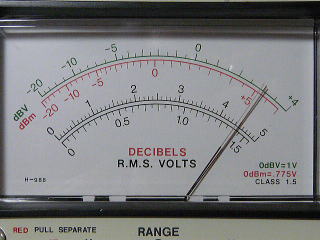 少し高くなっています。 |
| ①テープスピード調整 2020年8月24日更新 |
|
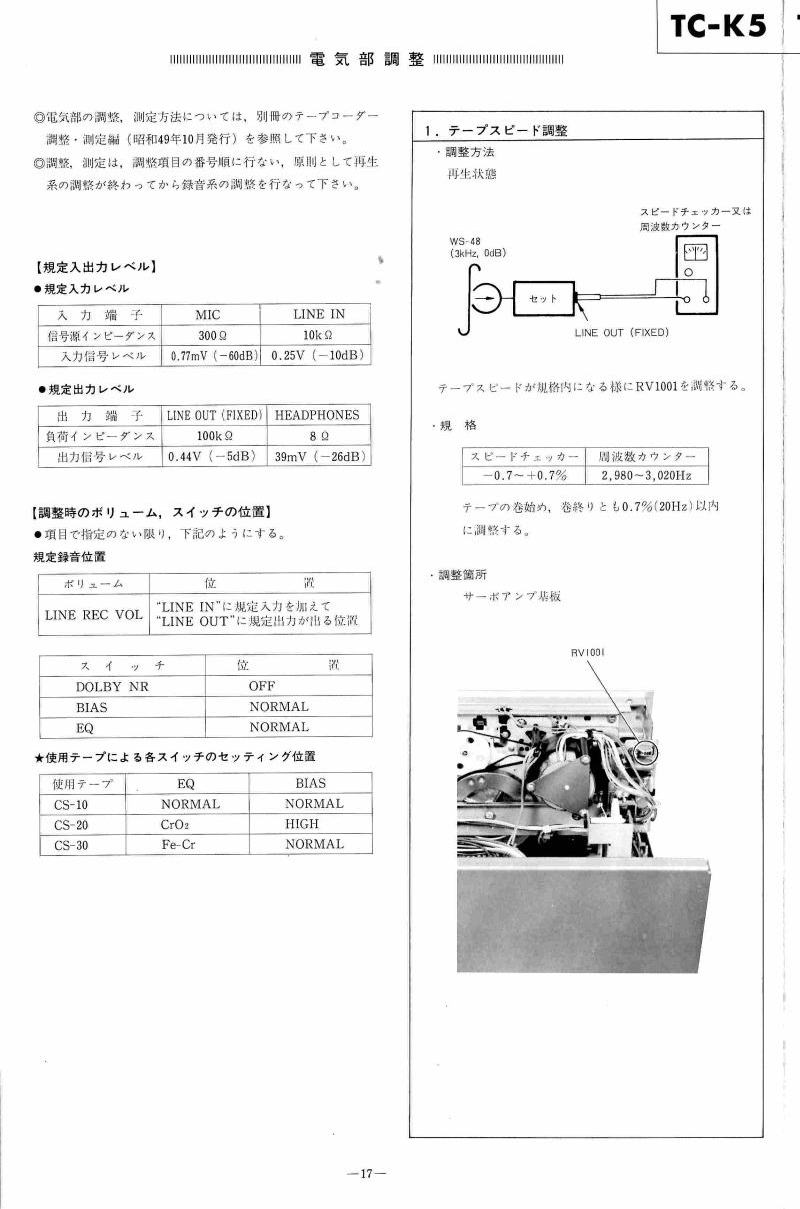 サービスガイドでは、3kHz/0dBのテストテープを使用します。 |
|
 GX-Z9100で製作したテストテープ。 |
 3kHzに合わせました。 |
| ②録再ヘッド垂直調整 (アジマス調整) 2020年8月24日更新 |
|
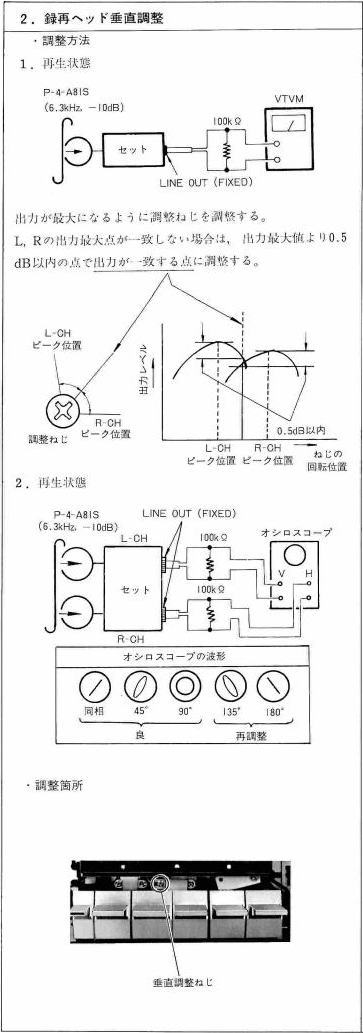 サービスガイドでは、6.3kHz/-10dBのテストテープを使用します。 |
|
 10kHzのテストテープを再生します。 |
 SONYのシングルキャプスタンのメカは、 サービスガイドでは6.3kHzを使用して います。 |
 10kHzは変動が多いです。 |
 規格内に合っています。 |
| ③再生レベル調整 2020年8月24日更新 |
|
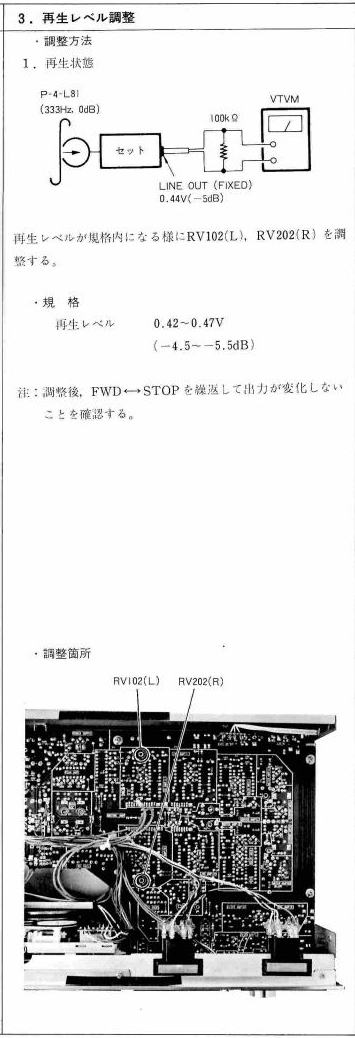 サービスガイドでは、333Hz/0dB(160nwb/m/-4dB/0VU)の テストテープを使用します。 再生レベル調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |
|
 315Hz 0VU(-4dB)のテストテープを再生。 |
 315Hz 0VU(-4dB)を表示。 |
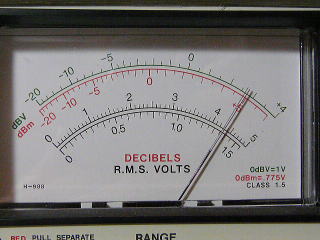 435mV -5dBに合わせ直します。 |
 一応、新品の315Hz 0dBの テストテープを再生。 |
 |
 |
 左右のレベルを合わせます。 |
 メーターは合っているようです。 |
| ④再生イコライザー調整 2020年8月24日更新 |
|
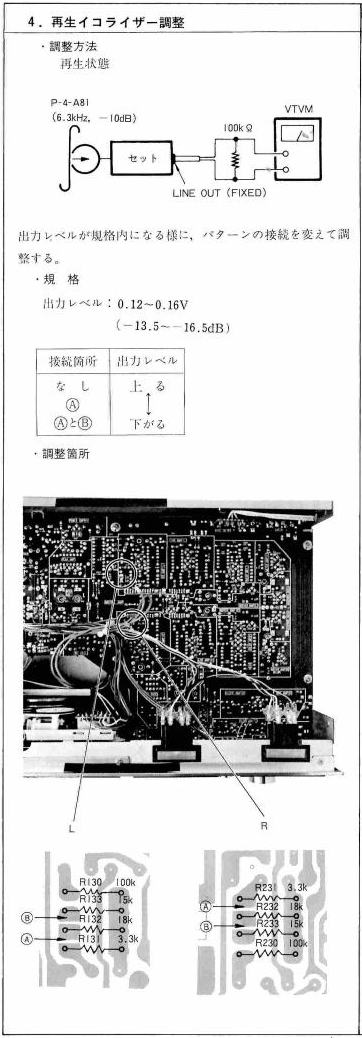 サービスガイドでは、6.3kHz/-10dBのテストテープを使用します。 再生イコライザー調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |
|
 10kHzのテストテープを再生。 |
 10kHzの再生レベル。 |
 左チャンネル再生イコライザー調整箇所。 |
 右チャンネル再生イコライザー調整箇所。 |
 パターンをブリッジして調整します。 ブリッジをすると10kHzのレベルが 落ちたのでパターンを分離した 状態に戻しました。 |
 左右対称になっています。 ブリッジをすると10kHzのレベルが 落ちたのでパターンを分離した 状態に戻しました。 |
| ⑤レベルメーター調整 2020年8月24日更新 |
|
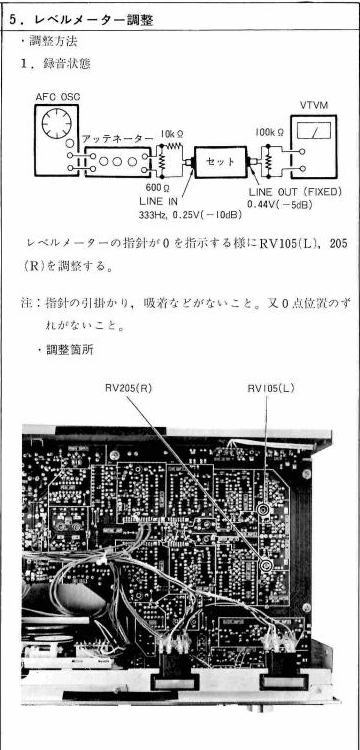 レベルメーター調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |
|
 333Hzの信号を入力し録音状態にします。 |
 ラインアウト固定出力が 333Hzを435mV -5dBで VUメーターが、0VUになるように 調整します。 |
| ⑥録音バイアス調整 | |
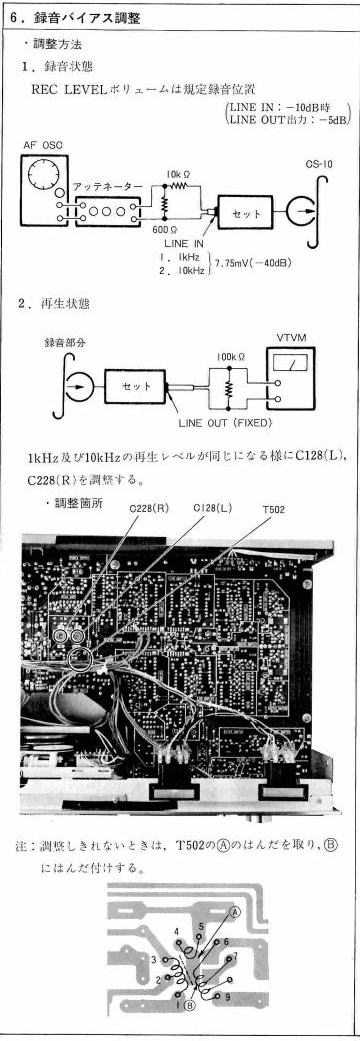 サービスガイドでは、1kHzと10kHzの-40dBの信号を使用します。 |
|
 333Hzと10kHzの-30dB信号が 録音と再生で同じになるように バイアスを調整しました。 |
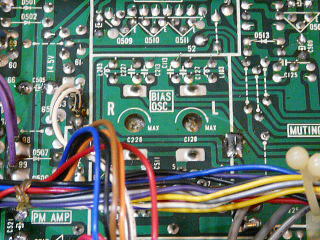 バイアスの調整箇所です。 新しいマクセルURをNORMバイアスで 合うように調整しました。 |
| ⑦録音レベル調整 2020年8月24日更新 |
|
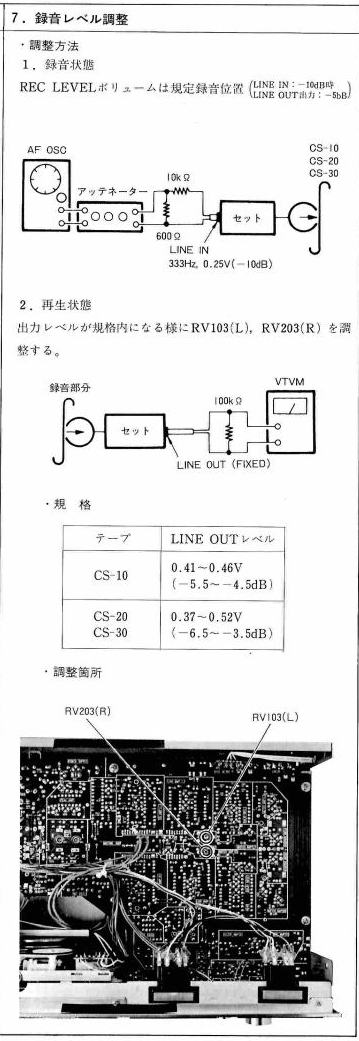 |
|
 |
 ミリバルのレンジを切換ます。 |
 435mV -5dBに合わせます。 |
 333Hzを435mV -5dB 0VUで録音し、 再生レベルも同じになるように 録音感度を調整します。 |
 バックテンショトルクと周波数と テープ個体差の関係について、 もう少し実験を続けます。 |
 アジマス調整後は、ヘッドの調整ネジに ペイントロックをします。 |
| ⑧19kHzフィルター調整 2020年8月24日 |
|
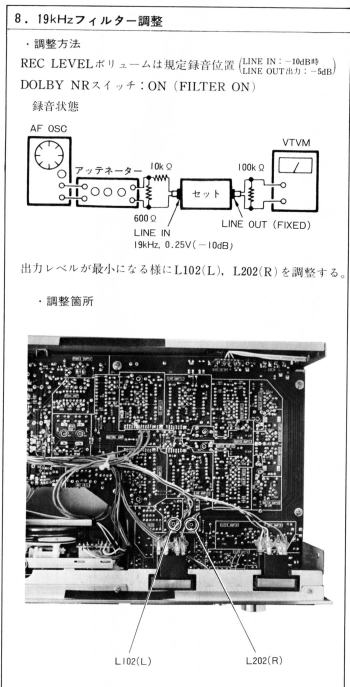 19kHzフィルター調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」をご覧ください |
|
★もう一台の整備は、 「SONY TC-K5の修理 PART2」へ★ |
|