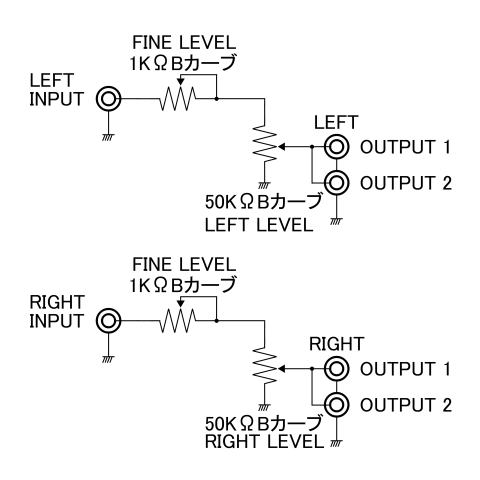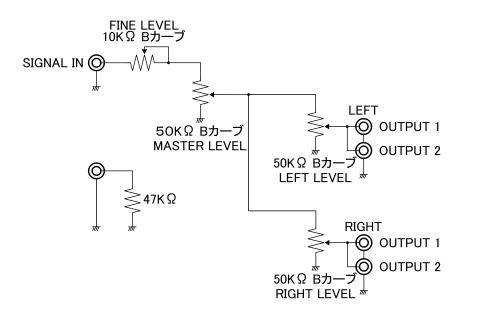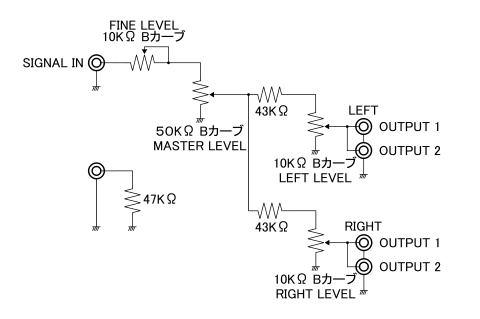| 回路図 | ||||
|
||||
| 部品 | ||||
 ケースは、タカチのYM-130 |
 MAV BR−20R ローレットつまみ 中
MAV BR−25R ローレットつまみ 大
|
 アルプス電気 ボリュームB1KΩ(FINE LEVEL) アルプス電気 ボリュームB50KΩ |
||
 マウントRCAジャック
(金メッキ、カラーリング付き、赤と白) |
 マウントRCAジャック(金メッキ、赤と白) こちらを、使用する予定です。 |
 1芯シールド線 |
||
| 工具 | ||||
 ミニパンチ ボリュームなどの穴あけに使います。 |
 穴を広げるリーマー、 穴をあけるシャーシパンチとミニパンチ |
 電動ドリル・ドライバーと、チタンドリル |
||
 ボリュームなどのナット回しに使用する、 ボックスレンチ |
 ヤスリ |
 クリンピングプライヤーは、コネクタの圧着、 被服のストリップ、ワイヤーの切断に使用 |
||
| 操作パネルと入出力端子用の文字シール製作 | ||||
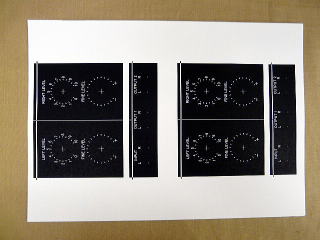 ラベルシートで製作してみました。 シャーシに貼り付けます。 |
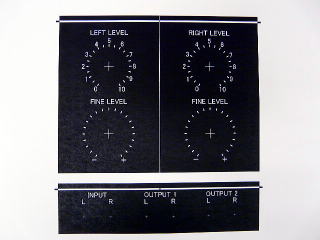 フェーダー操作パネルと 入出力端子 |
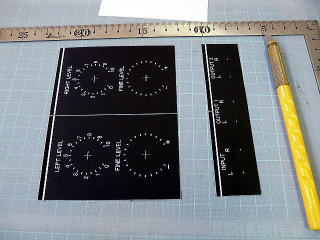 切り出します。 |
||
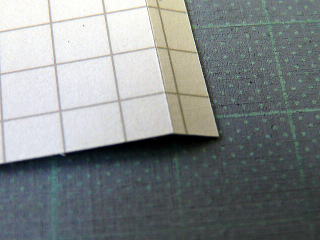 のりしろ部分の台紙に切れ目を入れます。 |
 のりしろ部分の表側。 |
|
||
| 操作パネルと入出力端子用の文字シールを貼り付ける | ||||
 ケースを開けます。 |
 裏パネルのセンター位置に印をつけます。 |
 蓋のパネルのセンター位置に印をつけます。 |
||
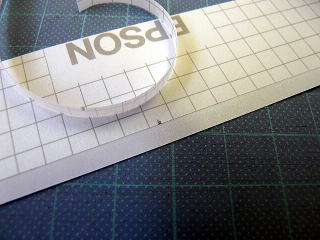 のりしろ部分の台紙を取ります。 |
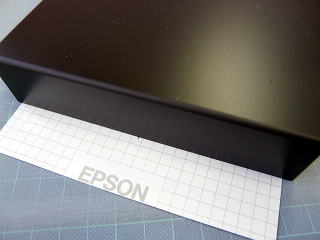 シールとケースのセンター位置を合わせます。 |
 のりしろ部分を貼り付けます。 |
||
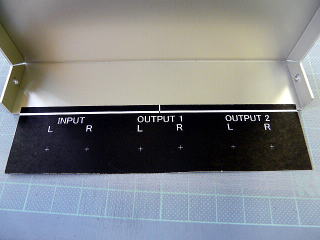 のりしろ部分をしっかり貼り付けます。 |
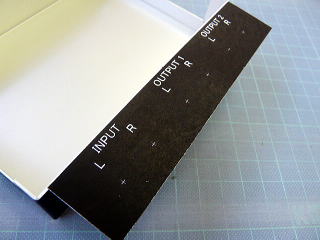 折り曲げます。 |
 入出力端子シールの台紙をはがします。 |
||
 きれいに貼れました。 |
 のりしろ部分を剥がします。 |
 のりしろ部分を切り取ります。 |
||
 のりしろ部分の台紙をはがします。 |
 センター位置を合わせます。 |
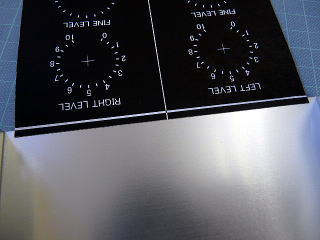 のりしろ部分を貼り付けます。 |
||
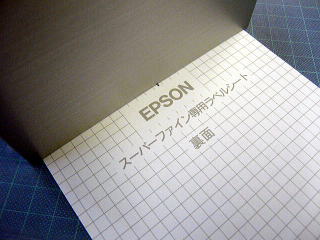 折り曲げます。 |
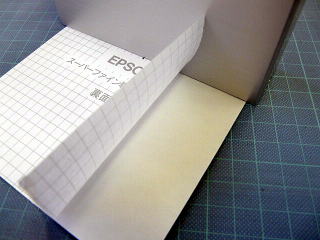 台紙をはがします。 |
 操作パネルのシールもきれいに貼れました。 |
||
 のりしろ部分を剥がします。 |
 のりしろ部分を切り取ります。 |
 組み合わせてみました。 |
||
| 穴開け加工 | ||||
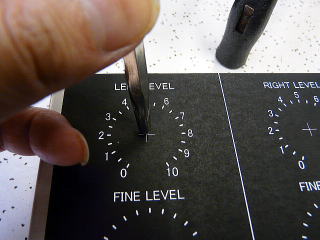 ポンチでドリルの位置決めをします。 |
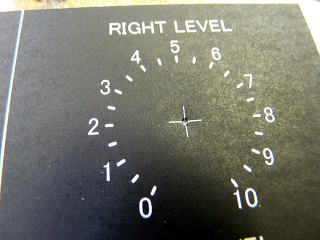 センター位置が少しへこみます。 |
 こちらも、センター位置を少しへこまします。 |
||
 携帯スタンドをドリルに取り付けます。 |
 ケースにネジを取り付けます。 |
 4ミリの穴を開けます。 |
||
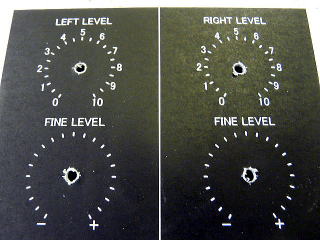 4か所開けました。 |
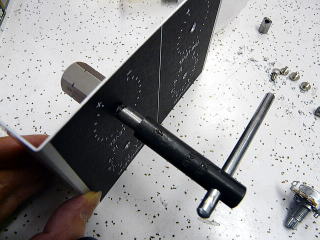 ミニパンチの登場です。 |
 ハンドルを回すとカッターがうすの中に入って、 綺麗な穴をあけることができます。 |
||
 バリも出ません |
 4か所とも綺麗に開きました。 |
 入出力端子に穴を開けます。 |
||
 両側の台を固定します。 |
 6か所穴があきました。 |
 バリが出ます。 |
||
 バリをきれいに削り取ります。 |
 リーマーで穴の大きさを調整します。 |
|||
| ボリュームとピンジャックの取り付け | ||||
 ボリュームの突起部分を加工をします。 |
 この突起部分をニッパーで少し削ります。 |
 折ります。 |
||
 簡単に折れます。 |
 ヤスリをかけます。 |
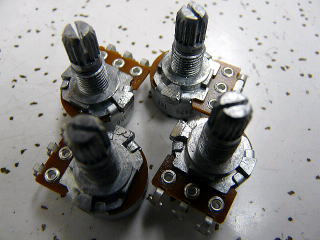 4つとも加工します。 |
||
 ボックスレンチでナットを回します。 |
 向い合せに取り付けました。 |
 4つとも取り付け終わりました。 |
||
 ピンジャックを傷付けない工具を使用します。 |
 端子の向きを揃えました。 |
 ピンジャックを6個とも取り付けました。 |
||
| 配線 | ||||
 クリンピングワイヤーで、シールド線の 被服を剥きます。 |
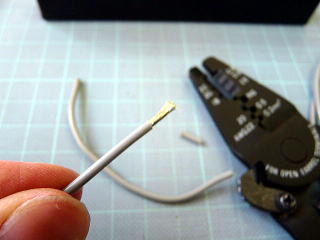 綺麗に被服が剥けます。 |
 次に、芯線の被服を剥きます。 |
||
 芯線の被服は、はんだ処理時に 溶けるため短めにします。 |
 8.5cm、9cm、12cm、20cmを2本ずつ |
 末端をはんだ処理します。 |
||
 フラックスは、酸化被膜の除去と 半田の乗りが良くなります。 |
 ピンジャックの半田付けをする部分に、 蓋についているブラシで塗ります。 |
 ボリュームの端子にも塗ります。 |
||
 8.5cmのシールド線を、 OUTPUT 2に半田付けします。 |
 8.5cmと12cmのシールド線のシールド同士を 数回ねじって繋げます。 |
 OUTPUT 1に半田付けします。 |
||
 20cmのシールド線を、 INPUT 1に半田付けします。 |
 12cmのシールド線の芯線を、 LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 真ん中の端子に半田付けします。 |
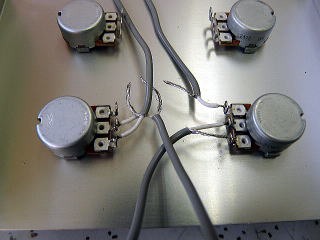 9cmのシールド線の芯線を LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 端子に半田付けします。 |
||
 9cmと12cmのシールド線のシールドを、 LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 端子に半田付けします。 |
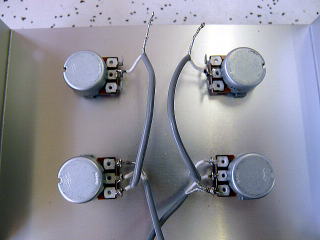 9cmのシールド線の芯線を、 FINE LEVELの真ん中の端子に 半田付けします。 |
 INPUT端子の20cmのシールド線の芯線を、 FINE LEVELの端子に半田付けします。 |
||
 シールド同士を半田付けします。 |
 熱収縮チューブを被せます。 |
 半田ゴテのコテ先の熱で収縮させます。 |
||
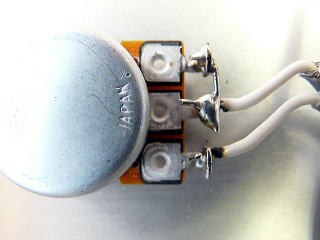 真ん中の端子と未使用端子を ジャンパー線で繋ぎます。 |
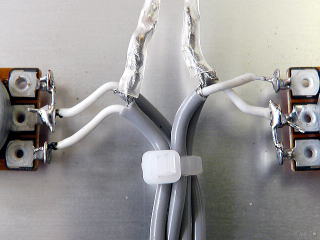 両チャンネルとも同じです。 芯線を長くして、繋ぐこともできます。 |
 約7cmの結束バンドです。 |
||
 結束バンドで、シールド線を束ねます。 |
 綺麗に束ねます。 |
 ケースをネジ止めします。 |
||
 そこにゴム足を貼り付けます。 |
 なるべく外側に貼ります。 |
 つまみを取り付けます。 |
||
 完成 |
 次は、テストです。 |
|||
| 動作テスト | ||||
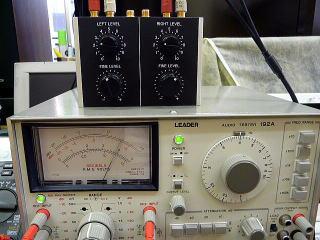 まずは、LEFT とRIGHTの LEVELの ボリュームで合わせます。 |
 FINE LEVELつまみで、微調整します。 |
 テスターのレベル差の補正も簡単です。 |
||
 FINE LEVELつまみの可変範囲を調べます。 |
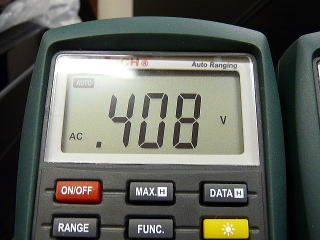 約8mVです。 |
FINE LEVELの可変範囲を もう少し広げる場合は、 5KΩBを使用します。 |
||
| 操作性向上のための改良 | ||||
|
||||
 5KΩ、10KΩ、20KΩ、25KΩ、50KΩの ボリュームをテスト用に買ってきました。 |
 最初に作ったケースは流用します。 ラベルをはがします。 |
 大変でしたが綺麗になりました。 |
||
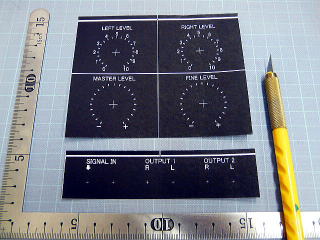 操作パネルと入出力の文字変更をしました。 バージョン1は、入出力のLRが逆でした。 |
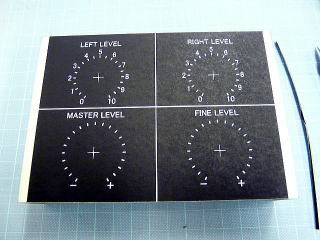 寸法は同じです。 |
 ラベルに、ボリュームの穴を開けます。 |
||
 4つとも開けました。 |
 入出力のラベルも張り替えます。 |
 ラベルに穴を開けます。 |
||
 ピンジャックの滑り止めと、 傷をつけないようにキャップも用意しました。 |
 キャップをつけると、 プライヤーが滑りません。 |
 ピンジャックを抑えながら、 ナットを回します。 |
||
 SIGNAL INは、色を変えています。 黒が入力で、茶色はダミー抵抗付です。 |
 アース側端子の向きを揃えます。 |
 ボリュームを取り付けます。 バージョン1の配線のほとんどを使用します。 |
||
 テストのため、結束バンドは使用しません。 |
 つまみを取り付けます。 |
 入出力側。 |
||
| 操作性向上のための改良バージョン3 | ||||
|
||||
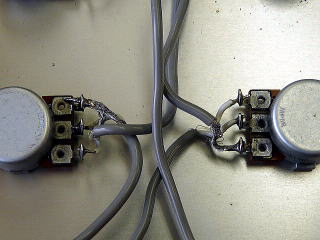 バージョン2の左右のレベル調整ボリューム 50KΩを取り外します。 |
 10KΩのボリュームと取り替えます。 |
 突起部分の取り外し加工します。 |
||
 10KΩのボリュームを取り付けます。 |
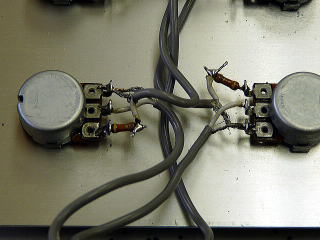 43KΩの抵抗と配線を半田付けします。 |
 結束バンドで固定します。 |
||